【事例】ユーザーの声はデザイン組織の武器である──パーソルキャリアがデザインプロセスにUXリサーチを取り入れたプロセスとその成果
「ユーザーを知らずに、どうやって顧客の課題を解決するのか?」──問題意識こそあったものの、そのために取り組みを始めることはなかなか難しい状況でした。
そこから1年半、定常的にユーザーの声を聞いて改善できるようになったデザイン組織は、パーソルキャリア社内の優れたチームとして表彰されるまでに至りました。
全く経験・知見のない状態から、どのようにして従来のデザイン・開発スピードを損なうことなくUXリサーチを武器として標準装備することができたのか。
取り組みスタートからのプロセスと成果を振り返ります。

パーソルキャリア カスタマーP&M本部デザイン統括部 古藤舞華様、水原秀幸様、エグゼクティブマネージャー 三輪亮様
UXリサーチに取り組む経緯:ユーザーの声なきプロダクトからの脱却
古川: この度は、社内表彰の受賞、誠におめでとうございます。これまで取り組まれてきたことが一つの成果として結実したと感じており、今日はこれまでの流れを一緒に振り返れればと思います。
では、まずは、なぜそういった体制が必要だと思われたのか、お聞かせいただけますでしょうか?
古藤: ポップインサイトさんにご支援をお願いさせていただいたのは、約1年半前になります。
当時、私たちの組織にはリサーチの経験や知見が全くありませんでした。リサーチがないということは、ユーザーの声が”デザイン組織””デザイン”において反映されていないということ。じゃあ誰の声でプロダクトができているかというと、社内のデザイナーやディレクターのディスカッションで決まっていくのですが、「もっとこれがいいんじゃないか」という話は出るものの、実際にユーザにとっていいものになっているのかというのは誰も答えや自信を持てずにいました。
なので、そこにデザイン観点でのユーザーの声を取り入れることで、ユーザーに求められる「正解」に近いところを目指していきたい。そんな思いから、サポートをお願いさせていただきました。
三輪: ジョブ理論などもそうですが、突き詰めると、「ユーザーを知らないのに顧客の課題って解決できないよな」と思ったんです。それが最終的なアウトプットのデザインに関わってくるのに、デザイナーが顧客を知らないというのは良くない。ディレクター組織とも連携しているのですが、もっとそういったことをやっていきたいと思い、ご相談したのが発端です。
古川: 今では月に2回、ユーザビリティテストを行って改善に取り組まれています。この月2回という数字は、どのように設定されたのでしょうか?

古藤: ユーザーの声を取り入れるからには、やはりなるべくたくさん調査を実施したいという思いがありました。また、常に複数の施策が動いている中でそれらをユーザーに見てもらい改善するフローを固めるためには、とにかくたくさんの調査を実施できるようにする必要があるとも考えました。
御社で行う調査は平均で1ヶ月半から2ヶ月近くかかっていましたが、もっと早く回していきたいという想いを踏まえ、具体的な目標として月2回という数字が出てきました。当時としてはかなり無理を言っている感覚でしたが、前例のない回数だという前提で様々な取り組みを進めていきました。
三輪:他社さんでUXリサーチの部署があって月何回も調査している事例があると聞き、そういう環境を作っていきたいと感じたのも背景にあります。
古藤: 探索型のニーズ把握調査に2ヶ月かかるのは、しっかりと分析する調査においては一定必要な期間だと思います。一方で、私たちデザイン組織として焦点を当てるべきは検証型のユーザビリティテストでした。ユーザビリティテストであれば月2回実施できるのではないかと考え、私たちの領域だからこそ目指したい数字でした。

本当はみんな興味があった、ユーザーの声を聞きたかった
古川: 月2回調査できるまでに1年以上かかったとのことですが、どのようにしてできるようになっていったのでしょうか?
三輪: 私たち側の成長もあったと思います。リサーチに参加する中で、その場でリサーチ結果についてディスカッションできるようにもなりました。ポップインサイトさんのご支援もあり、短期間でユーザビリティテストが回せるようになったのが良かったと思います。
戸田: 最初は私たちがリサーチして報告していましたが、だんだんパーソルさんのデザイナーさんが実査に同席してくださったのが大きかったですね。最初はトライアルから始めて、どんどんライトにして、月2回にしていきました。もちろんプロセスやテンプレートはポップインサイトが作成し整えていましたが、そんなことより、デザイナーさん自らが一緒に参加して一緒にメモを取り一緒に分析するという体制にできたこと、そこに積極的に取り組んでくれたことが最も大きな要因だったと思います。
水原: 「僕らデザイン組織からUI/UX改善をしていこう」という目標が元々あったので、最初からみんな意識は高かったです。UXリサーチに興味を持っているデザイナーがほとんどだったので、「みんなでやろう」とどんどん進んでいきました。「同席したい」「学びたい」という意識を共通で持っていたのが大きかったかなと思います。
僕自身の熱量も高かったので、「やろうよ」という感じで、ディレクター組織の方にも「隙あらばリサーチやりませんか?」と声かけしていましたね。
三輪: 水原さんは、HCD(人間中心設計)プロセスをメンバーにインプットしたり、勉強会も開いたりしていましたしね。
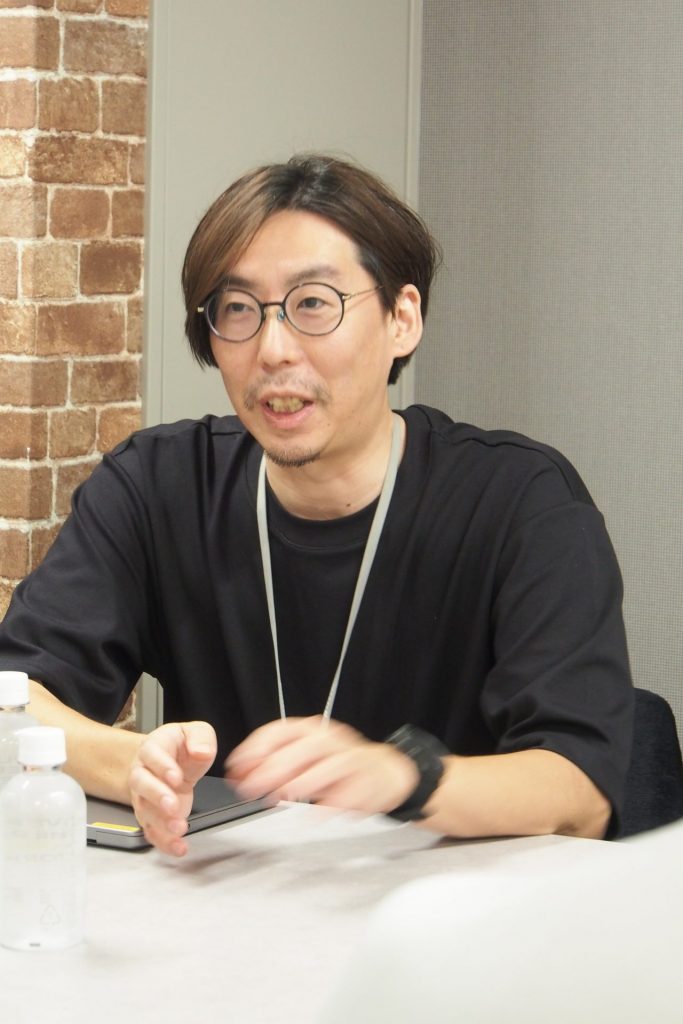
古藤: やってみてわかったのは、みんな興味はあったけれど「機会がなかった」「場がなかった」「何をどう進めればいいのか分からなかった」ということです。
直近では、領域を超えて実査のライブ配信にも取り組んでいて、半期で延べ100名ものデザイナーが参加してくれました。やはりみんなやりたかったんだなと思いました。
1年くらい経つと、メンバーから「ユーザーに聞いてみようよ」という会話が自然とできるようになり、当初やりたかった流れができてきたのはすごく良かったです。それが月2回のリサーチ枠も自然と埋まっていく状態につながっているのかなと思います。
デザイン組織に「リサーチ」という武器を作る0→1の挑戦と成果
古川: そういった取り組みが貴社内でも表彰されたとのことですが、どういったところが社内で評価されたのでしょうか?
古藤:1年半の取り組みでどれくらいの成果を可視化した点です。
最初の1年間はある意味「慣れ」の期間でしたが、しっかりと数を重ねナレッジも蓄積できました。また、実際に施策化しリリースしたものの効果も追跡していました。その結果、リリース件数や施策成果をできる限り金額換算し「おおよそこういうことができるようになった」と可視化できる状態になりました。これにより一緒に取り組んでないメンバーから見ても「こんなに良かったことがあったんだ」と感じてもらえ、評価に繋がったのかなと思います。
古川: 成果を取りまとめている資料を見せていただきましたが、ものすごい量でした。あれだけのことを時間かけて継続するのは本当にすごいことだと思います。
三輪: 最大のポイントは、やはりリサーチをやっていなかったデザイン組織の中で「リサーチ」という武器を作った、つまり0から1を生み出した点ですね。リサーチができる環境を作ったことによって、みんながユーザーを知る・触れる機会ができたこと。その中で大きな事業インパクトに繋がりうる施策を生むこともできました。
準備期間は大変でしたが、みんながユーザーテストの良さを感じてくれたこと、そして、この素晴らしい状態になったことに対して、皆さんが評価してくださったのだと思います。この賞は投票で選ばれるので、本当に報われたなという気持ちです。
水原: 勝てた案件(大きな事業インパクトに繋がりうる施策を生めたプロジェクトのこと)は、リサーチがなければ負けていたと本当に思っています。この案件では、僕らも気づけない観点でのフィードバックでしたので、リサーチのおかげで最初から精度の高い施策を出せたことで機会損失をなくせましたし、手戻りを減らすなど開発コストの削減にも繋がりました。開発前にデザイナーがユーザーの声を聞いてブラッシュアップできたからこそ勝てた。これは大きな価値です。
三輪:ちなみに、僕はこの支援の稟議を通すときにデザインツールと同じだと説明しています。デザイン精度を高め、事業成果を上げるための武器だと。それくらいデザイン組織においてリサーチというのは強力だと感じていますし、経営にも納得してもらえていますね。
ポップインサイトの支援内容:柔軟性と伴走、そしてナレッジの共有
古川:これまで一緒にそういった成果創出に取り組んできましたが、その中で、ポップインサイトと契約して良かったと感じていらっしゃるところはありますか?
古藤: 伴走してもらえている感が強かったですね。
おかげで「何をしていいかわからない」「時間がない」といった初期の課題はほぼ解消しました。一緒に推進してくれるパートナーは重要だと感じましたし、私たちの手が届かないところを我が事のようにやってくださる存在がありがたかったです。提案してくれる姿勢や、逆に「こういう課題があるから難しい」と正直に言ってくださった上で「こういうやり方ならできる」と具体的な解決策を提示してくれる会話もありました。
水原: 常にいていただけるという点も、私たちのハードルを下げてくれました。気軽に相談できる環境が、すごくやりやすいですね。都度となると「ちゃんと準備しなきゃ」とこちらも構えてしまうのですが、そういったこともなく定例やSlackでカジュアルに相談できるので、まず「やってみよう」という場がある。だから、まず参加してみて、実践して、次のステップへと、どんどん繋げていけたのは大きかったと思います。

三輪: 私の目線では、リサーチだけでなくメンバー・組織を教育してくれる点です。私たちの組織もかなり強化されました。外部のパートナーというよりは、中で一緒にやってくださっている「仲間」となってくださったのが、本当にすごく良かったなと思います。色々なリサーチ会社さんとやり取りしてきましたが、そこが一番ポップインサイトさんとやって良かったと感じる部分ですね。
古藤:一緒に会話する時間がより増えていけば行くほど関係性や仕組みの密度が高まっていくんだろうな、と感じますね。
教育という観点では、ポップインサイトさん全体の知見・ナレッジを展開してくださるのもすごく頼りになっています。「御社(ポップインサイト)ではどうしていたか」「こういう事例があるか」といった質問に、必要に応じてポップインサイトさん内で確認したり調べてくださった上で取りまとめて教えてくださるのがとても良いです。
パーソルキャリアが今後目指すところ
古藤: デザイン統括部として目指しているのは、ご協力いただいた調査結果をきちんと施策化して、価値ある案件にすることです。施策化の部分はまだやれることがあると思うので調査結果を自分たち以外の人にも違和感なく伝わるものにして、当たり前にできるようになる状態を目指しています。
水原: もっとスピードを早めるのは難しいかもしれませんが、定常的にずっとリサーチが回っている状態を作りたいです。また、定性的なユーザーの声を常に取得して貯めていく仕組みを作りたいと思っています。定量データの情報だけでなく、うまく定性・定量を掛け合わせて施策のスタートを切ったり、検証の振り返りもできる形を作っていきたいです。
デザイナーが、今以上に事業を自分ごと化する
古川: 最後に、同じような課題を持っている会社・組織へのアドバイスをお願いします。
水原: デザイナーには「ユーザーのことを知りたい」「自分のデザインはどう思われているんだろう」といった欲求・興味は絶対にあると思います。そういったデザイン組織の中でリサーチに取り組めていない、環境がないと感じている方たちは、ぜひ最初のゼロフェーズからポップインサイトさんと作り上げていくことができると思うので、気軽にポップインサイトさんに声をかけてみてほしいです。
三輪:リサーチを通じて、 デザイナーが事業を自分ごと化する、という効果もあると思います。ユーザーを知ることによって、事業と近くなって、デザインしていくのがより楽しくなる。そういう側面も、今回の取り組みを通じて感じました。
古川:みなさん、お忙しいところ、本当にありがとうございました!!
