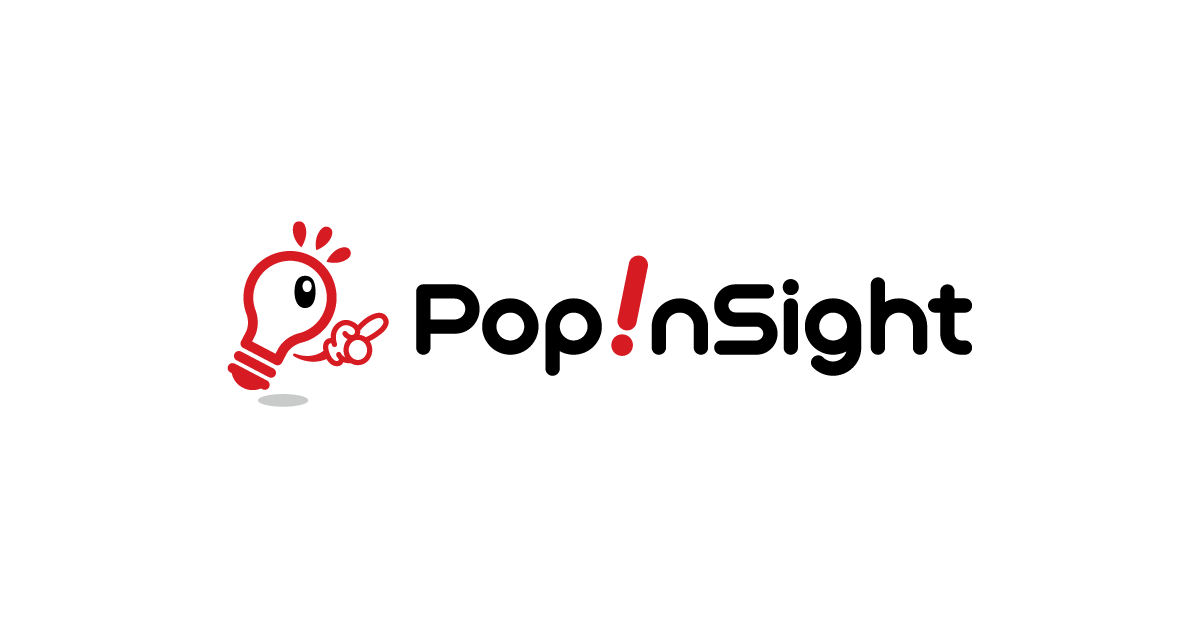Webマーケター育成ツールとしてのユーザーテストの効能
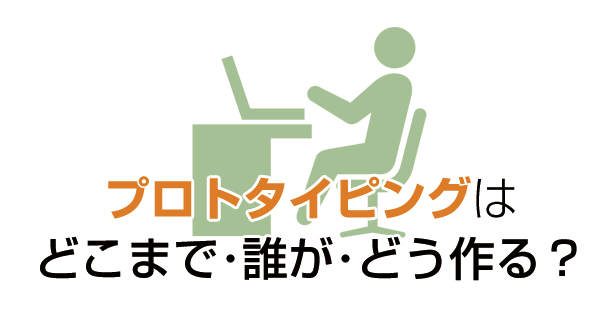
普段は「仮説立案ツール」「ビジネス成果創出ツール」としてユーザーテストを紹介することが多いですが、実は私は、ユーザーテストの一番の価値は「人材育成ツール」としての効果だと思っています。
例えばあるサイトのデザインを作る場合、その正否(良いか悪いか)は、現在ほとんどの場合、クライアントか社内上司に判断を仰ぐプロセスになっていると思います。 しかし本来デザインの良し悪しは、そのデザインを使うユーザーがそれを使いやすいと思うのか(コンバージョンするか)によってジャッジされるべきです。それにより、デザインは自身の失敗を強く自覚でき、成長に繋がるのです。
【無料ダウンロード】ユーザビリティテストの基本
数あるUXリサーチ手法の中でも最初に始めやすい「ユーザビリティテスト」の「基本的な設計・実査・分析の流れ」と「実施の進め方や注意点」を解説します。
ビービット時代の「鬼コーチ」としてのユーザーテストの思い出
ビービット2年目のあるプロジェクトで、自分としては自信満々で作った画面設計をクライアントに意気揚々と提案しました。クライアントもまずまずの反応です。 その画面設計を用いて、1回目のユーザーテストに臨みました。
1人目のユーザー、ある状況設定の元で画面設計を提示すると「…すぐ前のページに戻りますね」という、非常につれない反応。 2人目のユーザー、「うーん…よくわからないので戻ります」。 結果的には8名中7名から「よくわからない」「使わない」という無慈悲な評価を得ることになりました。
当初の想定では、このユーザーテストで「バッチリです!」と報告すべきはずでしたが、現実は残酷です。
- 自分の能力不足への恥ずかしさ
- 自信満々に提案したクライアントへの気まずさ
- プロジェクトスケジュール上の修正可否の不安
と、非常に辛い状況に追い込まれました。そこからプロジェクトの終わりまでは、もちろん徹夜続きのお祭り状態です。しかし、この辛い結果を踏まえて全面的に方向性を見直し画面設計を作り替えた結果、2回目のユーザーテストでは4名中3名をコンバージョンさせることに成功しました。
結果的にこのプロジェクトは大成功し、クライアントの社内表彰に選ばれるほどの成果を出すことができました。
「失敗の自覚」と「成功体験」がグロースハック力を育てる
上記プロジェクトで、もしユーザーを行わずにリリースしてしまっていたら、結果は酷いものだったでしょう。そしておそらく、そうなっても自分の非ではなく「集客施策がミスったのでは」「時期的に仕方ない」等の言い訳を探していたと思います。
上司やクライアントは、スケジュール等の背景を理解してしまっているがゆえに、現実を見た妥協案を考えたり、強い指摘がしづらい状況になりがちです。 また、仮に上司やクライアントから指摘があったとしても、制作者としては「自分の方が詳しい」「現場をよく分かってないくせに」等と、反抗的な意識を持ってしまいがちです。
しかし、ユーザーテストでは、ユーザーは背景など全く関係なく、純粋にそれが自分にとって「良いか悪いか」という反応を返してきます。 またユーザーテストの結果が悪いものだった場合、その原因が自分の作ったデザインやコンテンツのダメさにあることは明らかで、上司やクライアントに責任転嫁することはできません。
アルコ社の黒須さんは「ユーザーテストの結果を見るのは心が痛い」と仰っていましたが、非常に同感です。まさに良薬は口に苦しです。このユーザーテストという「鬼コーチ」の鉄槌を受けることで、「これでは駄目だ」ということを肌身にしみて自覚することができ、それが改善や最終的な成功(グロースハック)に繋がるのです。 そしてこの経験を何度も経ることで、いやがおうにも成長していきます。
できるデザイナーは、言われなくても勝手にユーザーテストをしている
大学時代の後輩で、非常に才能に満ち溢れたデザイナーがいます。 彼は100人規模のデザイン会社でエースとして活躍しているのですが、いわく「他の人はユーザーテストなんてやってないけど、僕はデザインの後、友人やバイトを捕まえて必ずユーザーテストしてます。
実際のターゲットに見せないと、そのデザインが良いかどうかわからないじゃないですか」と言っていました。 本当にできるデザイナー、「キレイに作る」でなく「良いものを作る」ことにこだわるデザイナーにとっては、ユーザーの審判を仰ぐことは業務上当然のプロセスなのです(これはもちろん、エンジニアやディレクタなど、全ての職種に当てはまります)。
人材育成の仕組みとしてユーザーテストを定常的に行うべき
経営視点で見ても、ユーザーテストを定常的に行うプロセスを構築することは、クライアントへの提供価値を高めるだけに留まらず、人材育成ツールとして強力に機能します。
P&G等のマーケティングに強い企業では、新製品がリリースされるプロセスに、アンケートや消費者インタビュー等の「ユーザーの関門」が必ず設けられています。これをクリアできない商品はリリースできない仕組みになっているそうです。このプロセスが「マーケターを取るならP&G」と言われるような強い育成体制を築いているのでしょう。
ビービットで現場のコンサルとして悪戦苦闘した経験からも思うことですが、Webマーケティングに関わる人間は、もっと「ユーザーの洗礼」を浴びるべきでしょう。 実際のアウトプットを作るディレクタやデザイナーでユーザーテストをやったことがないのは、クライアントに提案したことがない営業マンのようなものだと個人的には思っています。
正直なところ、自分の作ったアウトプットが、言い訳しようもなく失敗する経験は非常に辛いのですが、そこを乗り越えた後にはじめて、真の達成感や喜びを感じ、また成長できるのではないでしょうか。
実は私は元々は、ワークショップやユーザーテストノウハウの普及によって「ユーザーに触れる機会が少ない」という課題を解決しようと思っており、ビービット時代にも勝手に勉強会などを開いてその普及に向けて試行錯誤をしておりました。 しかし「現場のリソースが圧倒的にない」という状況下で、本格的なユーザーテスト(自分でユーザーテストを行う)のは現実的には非常に困難であることが分かりました。
弊社のユーザーテストExpressなら、金曜日までにプロトタイプを仕上げ、土日で勝手にテストを走らせ、月曜日に結果を見て修正、というような現実的なプロセスも実現可能です。そして、手軽ではありながらも、「鬼コーチとしての指導力(調査の品質)」には最大限こだわったサービス開発を日々継続しております。
このような体制構築を真剣に検討したいという経営者の方がいらっしゃいましたら、確実にお役に立てると思います。ぜひぜひお声がけください。
ユーザビリティテスト/ユーザーテスト
ユーザビリティテスト/ユーザーテストサービスとは、Webサイトやアプリをターゲットに近しいユーザーに使ってもらい、その様子を観察することで、ユーザー心理や行動、...
無料DL|ユーザビリティテストの基本

数あるUXリサーチ手法の中でも最初に始めやすい「ユーザビリティテスト」の「基本的な設計・実査・分析の流れ」と「実施の進め方や注意点」を解説します。