Works
事例

【事例】ユーザーの声はデザイン組織の武器である──パーソルキャリアがデザインプロセスにUXリサーチを取り入れたプロセスとその成果
- UXデザイン伴走/内製化支援(UXRO)
- UXリサーチ
- デザイン
- 人材
- UXデザイン体制構築
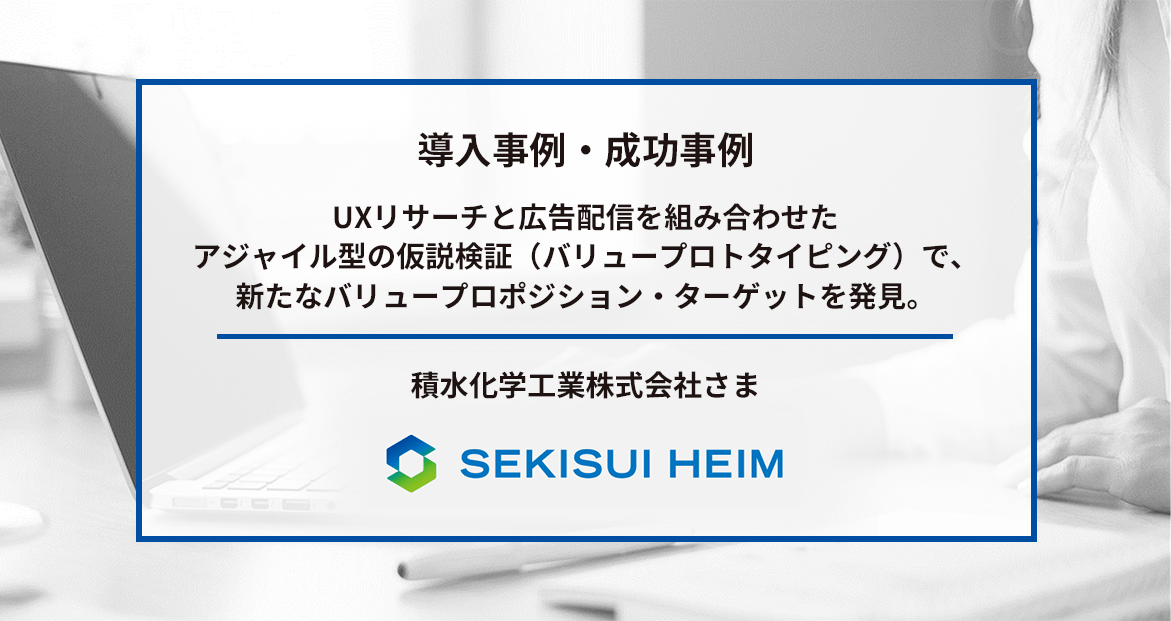
UXリサーチ×広告配信によるバリュープロポジションの探索支援(積水化学工業株式会社さま)
- UXリサーチ
- 新規事業/戦略/開発

【ビジネスアイデア創出事例】北欧型デザイン思考のワークショップを活用し、脱炭素・気候変動をテーマとしたビジネスアイデアの創出・グループ会社横断プロジェクト推進に貢献(三菱マーケティング研究会・三菱CC研究会)
- DX、新規事業創出、サービス開発
- 新規事業/戦略/開発

【金融事例】 金融商品診断ツールの運用改善/インタビュー調査
- UXデザイン伴走/内製化支援(UXRO)
- ユーザーテスト/ユーザビリティテスト
- インタビュー調査
- アンケート調査
- UXリサーチ
- 金融・保険
- リニューアル

【事例】ユーザーの声やニーズをスピーディーに把握・活用できるようになり、ソリューション開発の効率化につながった|大同生命保険
- UXデザイン伴走/内製化支援(UXRO)
- ユーザーテスト/ユーザビリティテスト
- DX、新規事業創出、サービス開発
- インタビュー調査
- アンケート調査
- 新規事業/戦略/開発
- 金融・保険

【事例】ユーザーテスト結果から得られた改善施策をベースに、すぐに改善へと動くことができた|三井住友銀行
- UXデザイン伴走/内製化支援(UXRO)
- ユーザーテスト/ユーザビリティテスト
- サイト改善
- マーケティング
- 金融・保険

日産自動車株式会社
- UXリサーチ
- メーカー
- 自動車

【事例】リーズナブルかつクイックに高品質なユーザー調査が行えて、社内のリソースの余裕にもつながった|サントリーホールディングス
- UXデザイン伴走/内製化支援(UXRO)
- DX、新規事業創出、サービス開発
- マーケティング
- サービス改善
- メーカー

【事例】ユーザビリティ調査の結果、顕在層と潜在層の異なる課題が明らかとなり、今後のUX改善につながるヒントが得られた|Sasuke Financial Lab
- ユーザーテスト/ユーザビリティテスト
- サイト改善
- メディア・出版
- マーケティング
- UXリサーチ
- 金融・保険

【事例】最大3分の1に調査工期を圧縮でき、調査コストを約50%カットできた|ロイヤリティ マーケティング
- UXデザイン伴走/内製化支援(UXRO)
- DX、新規事業創出、サービス開発
- サービス改善
- デザイン
- 情報・通信
- プロダクト
- 事業・サービス
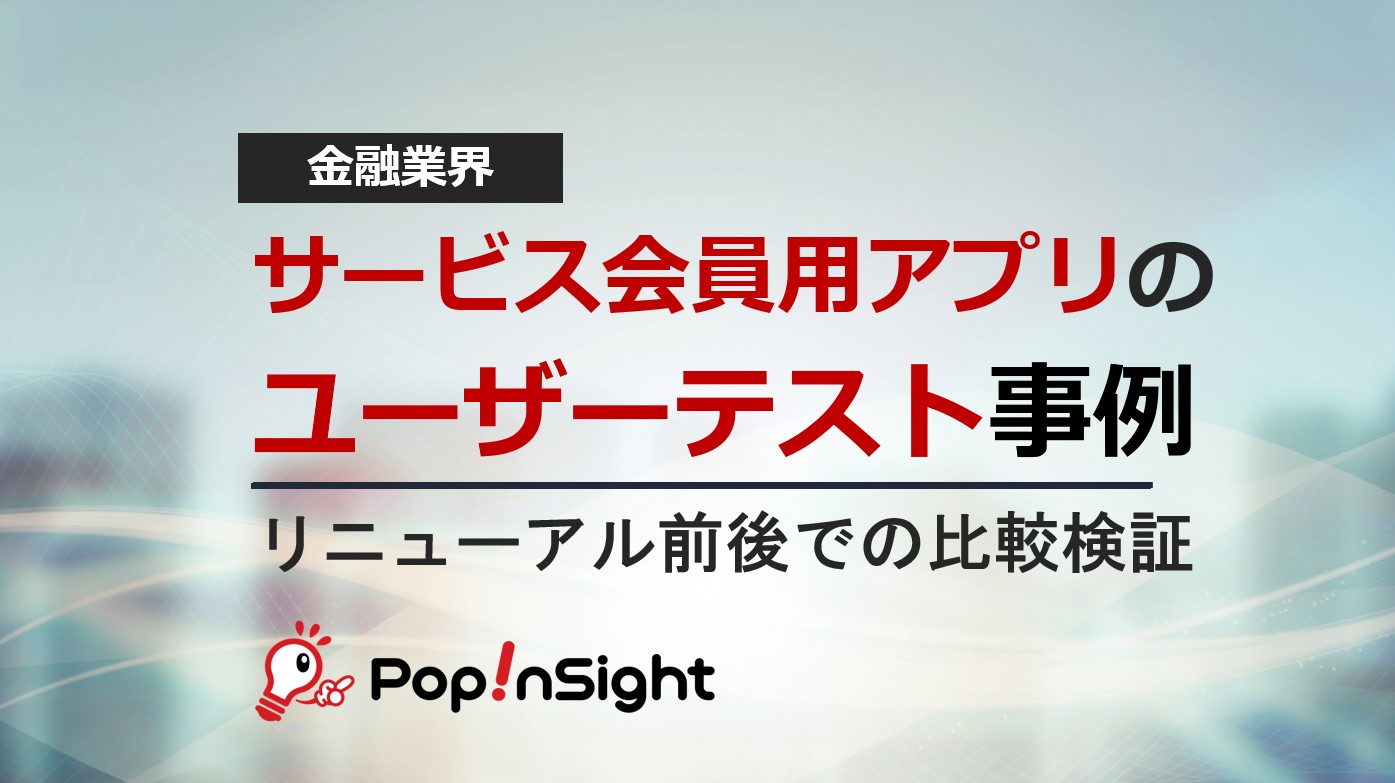
【金融事例】サービス会員用アプリのリニューアル前後での比較検証/ユーザーテスト
- UXデザイン伴走/内製化支援(UXRO)
- ユーザーテスト/ユーザビリティテスト
- アンケート調査
- UXリサーチ
- 金融・保険
- アプリ改善

第一生命保険株式会社
- UXデザイン伴走/内製化支援(UXRO)
- 金融・保険
オンライン出張相談(無料)
お受けしています! UX専門家があなたの気になることにお答え!

- 他社の事例を知りたい
- 上司をうまく味方につけたい
- 組織で取り組めるようになりたい
- 事業をユーザー中心に変えていきたい