第2回「ペルソナとユーザーモデルの違い」
第1回では「ユーザーモデル」の考え方について、「消費行動傾向」を例にしてご紹介してまいりましたが、イメージ頂けましたでしょうか。
第2回の今回は、ユーザーモデルを活用する商談の中でよく話題にもなる「ペルソナとユーザーモデルの違い」についてご説明して参りましょう。
第1回では「ユーザーモデル」の考え方について、「消費行動傾向」を例にしてご紹介してまいりましたが、イメージ頂けましたでしょうか。
第2回の今回は、ユーザーモデルを活用する商談の中でよく話題にもなる「ペルソナとユーザーモデルの違い」についてご説明して参りましょう。
2023年12月にメンバーズ社員に向けて「ペルソナの作成・活用」に関するアンケート調査を実施したので、本記事ではその結果についてご共有します。UXリサーチやUXデザインについて勉強中の方、ペルソナについてさらに知りたい方に向けた内容となっております。
「ペルソナ作成の元にするデータはどのようなものがあるのだろう」「ペルソナを使うメリットとは一体何なのか」「ペルソナはどのタイミングでアップデートさせるべきなのだろうか」といった疑問がある方は、ぜひご覧ください。
ジェイミー・レヴィ氏(以下、ジェイミー)の「UX Strategy: Product Strategy Techniques for Devising Innovative Digital Solutions」(第1版和書「UX戦略 ―ユーザー体験から考えるプロダクト作り」)は、デジタルプロダクトに関わる者にとって必読の本です。
本記事では、ジェイミー・レヴィ氏が提唱する「UX戦略」について、分かりやすくまとめている記事をご紹介します。
※本記事は著者Matylda Siuta氏より許可を得て翻訳したものです。
元記事:”UX Strategy Framework: Jaime Levy’s Must-Know Insights for Innovators” February 3, 2022
本記事はatama plus株式会社より許可を得て掲載しています。
元記事:” 【増補版】ペルソナ浸透事例で読み解く!UXリサーチを全社活用するatama plusの大切にすること”
こんにちは。atama plusというAI×教育のスタートアップでUXリサーチャー/UXデザイナーをしていますnozawaです。
先日、ポップインサイトさん主催のウェビナーで「ペルソナ浸透事例で読み解く!UXリサーチを全社活用するatama plusの大切にすること」というテーマでお話をさせていただきました。
本記事は著者Cindy Brummer氏より許可を得て翻訳したものです。
元記事:UX Booth ”Rethinking User Personas” August 31st, 2021
カスタマージャーニーマップとは、ユーザーが自社サービスやプロダクトを知り、利用や購買するまでの行動・思考・感情など、ユーザー体験(UX:ユーザーエクスペリエンス)のプロセスを時系列に可視化したものです。今や、カスタマージャーニーマップは、マーケティングの現場から、社内におけるユーザーへの共通認識の醸成まで、広く利用されています。
そしてこのカスタマージャーニーマップの作成にあたり、対象とするユーザー像として設計したものを「ペルソナ」と呼びます。本稿では、カスタマージャーニー成功の要となる「ペルソナ」について、現状の課題を指摘し、設計に欠かせない重要なポイントとは何かを説明したUX Boothの記事 ”Rethinking User Personas”をご紹介します。
自分がなにをしているのかがわかっているなら、それは研究とは呼ばない。そうは思わないかい? – Albert Einstein ユーザーリサーチは、UXのプロセスの一部となるかなり前から存在していたものです。1900年代初頭、Frank Gilbreth氏とLillian Gilbreth氏によってモーションスタディが世に知れ渡るようになりました。効率についてより深く理解するために、彼らは建築現場……
[caption id="attachment_77273" align="aligncenter" width="1024"] Bugatti Veyron by M 93[/caption]Bugatti Veyronという車(上図)は信じられないほど速く走る車です。まるでボンネットの下に1000頭以上の怒れる馬がいるかのように、時速60マイルまで2.5秒もかからずに加速します。直線であれば、……
次の話は、現在のIT企業ではよくある場面です。 マーケターのMaryには新プロダクトの案がありました。このプロダクトは大成功を収めると考えたMaryは、技術部にシステム構築を依頼しに行きました。開発者のDianeは、Maryの案を聞いてシステム構築をはじめると言いました。Dianeは機能を作り上げていくうちに、ある部分を組み合わせてほかを除けば、もっと効率の良いプロダクトになると気がつきました。……
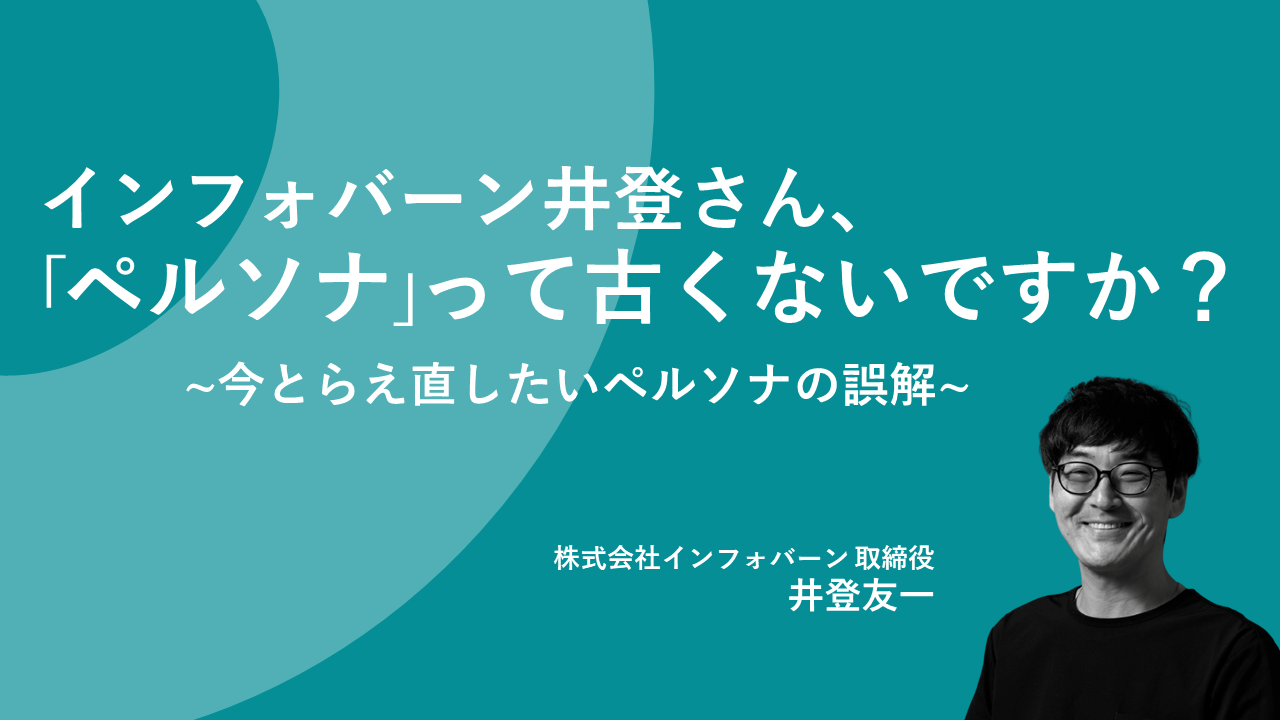
「ペルソナ」は、製品やサービスの顧客像をとらえる一般的な手法です。
しかし、実際に自社顧客のペルソナを作ってみると「こんなに限定的なペルソナが本当に使える?」「このペルソナは正しいの?」と悩む方も多く見受けられます。
「ペルソナは必要ないのでは?」「古い手法では?」・・・そんな疑問にお答えくださったのが、株式会社インフォバーンのデザイン・ストラテジスト、井登 友一さんです。井登さんは、過去20年以上ペルソナ作成にたずさわってこられた、言わばペルソナの専門家です。
2020年8月31日に開催されたセミナー「インフォバーン井登さん『ペルソナ』って古くないですか?~今とらえ直したいペルソナの誤解~」では、「デザインペルソナ」が誤解されがちな点や、ペルソナ作成中や作成後の活用の段階で悩みが生じやすい・混乱を招きやすい点について理解を深める問題提起をしていただきました。
ターゲットとなるオーディエンスを代表するようなペルソナの作り方については多くの記事が書かれています。しかし、そうした架空の人物に付ける名前については、これまでほとんど気にされていませんでした。物に名前を付けたくなるのは人間としてごく当たり前の性質です。女子高生のペルソナを単に「学生ペルソナA」と呼ぶのではなく、「マーサ」と呼んだとしたら、インパクトは違ったものになるはずです。現実の人々と同じように……